第10回:AI × 構造的プロンプト“BRIDGE”モデルで実現する“設計”とは?

ラーニングデザインにおいて、「何を教えるか」だけでなく「どう成果につなげるか」を明確にすることは、ますます重要になっています。第8回では、学習目標と評価戦略の関係性について考察しました。また、第9回では、研修の効果測定のカークパトリックモデルの考え方を中心に、研修の成果をどう定義し、どのように測定するかについて、学習成果の設計やデータ収集の視点から考察しました。特に、業務における成果をどう捉えるかは、研修設計の質を左右する重要な要素です。今回はその延長として、AIを活用した研修設計の可能性を探ります。
現在、AIを活用して研修構成や教材案を設計するケースが増えています。しかし、AIに対して曖昧な依頼をすると、期待したアウトプットが得られないことも…。そこで注目したいのが、BRIDGEモデルを活用した構造化プロンプトによる設計です。
今回のコラムでは、BRIDGEモデルの概要と、AIに研修設計を依頼するための実践的なテンプレート、そして担当者に求められるスキルについてご紹介します。
🔍 BRIDGEモデルとは?
BRIDGEは、研修設計に必要な要素を6つに分解し、AIに対して明確な依頼を行うためのフレームワークとして考えました。従来の設計理論(BloomのタクソノミーやABCDモデル)をベースに、AIとの対話を設計支援に活かすための構造を提供します。
| 要素 | 内容例 |
|---|---|
| Bloom Level | 研修で目指す認知レベル(例:Apply, Analyze) |
| Role | 対象者(例:新任マネージャー、中堅社員) |
| Intent | 学習目的(例:課題分析力の育成) |
| Degree | 達成度の基準(例:演習でチェックリストの80%以上達成) |
| Goal | 実務でできるようになること(例:改善提案ができる) |
| Evidence | 成果測定方法(例:提案件数、業務改善指標)※未定でもAIに提案依頼可能 |
BRIDGEモデルの図解
以下の図は、各要素の関係性と設計の流れを示したものです。
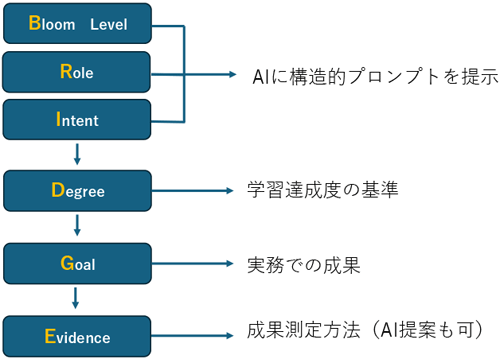
この構造に沿って情報を整理することで、AIはより的確な研修設計案を提示できるようになります。
🧠 ラーニングデザイナー(研修設計担当者)に求められる基本知識
- 研修の目的と背景を明確にする力(何のために研修を行うのか)
- 対象者の業務や課題を理解していること(現場との接点)
- 学習目標の設計スキル(ABCDモデルやBloomタクソノミーの理解)
- 成果測定の視点(行動変容や業務成果にどうつながるか)
🛠️ AIに研修設計を依頼するプロセス
このプロンプトモデルを使ってAIに学習コースや研修の設計を依頼するステップは、以下です:
- ステップ1:目的と対象者を明確にする
- 例:「中堅社員に業務課題分析力を身につけさせたい」
- ステップ2:BRIDGEモデルに沿って情報を整理する
- 各要素を記述する(下記テンプレート参照)
- ステップ3:構造化されたプロンプトを作成する
- AIに依頼する際は、6要素を含めた明確な文章にする
- ステップ4:AIからの提案をレビュー・調整する
- 提案された研修構成や演習内容を現場に合わせて調整
✏️ プロンプト作成のポイント
- 曖昧な表現を避ける:「良い研修」ではなく「Analyzeレベルで課題を構造的に捉える力を育成する」など具体的に
- 手法が未定でもOK:「ケーススタディが適切かどうかは未定なので、他の手法も含めて提案してください」と記載
- 成果指標を明示する:「提案件数」「上司評価」「業務改善指標」など、測定可能なものを指定する
🧪 プロンプト例(中堅社員向け)
| Bloom Level | Analyzeレベル |
|---|---|
| Role | 入社5〜10年目の中堅社員 |
| Intent | 業務における課題を構造的に捉え、改善の方向性を見出す力を育成する |
| Degree | 研修内の演習で、課題分析フレームを用いて論理的に課題の構造を説明し、チェックリストの80%以上を達成する |
| Goal | 実務で業務課題を構造的に分析し、改善の方向性を上司やチームに提案できるようになる |
| Evidence | 改善提案の提出件数、上司による提案の妥当性評価、業務改善指標(作業時間短縮、エラー減少など) |
| プロンプト文 | 「あなたは人材育成コンサルタントです。BRIDGEモデルに基づいて、中堅社員向けの業務課題分析力育成研修を設計してください。研修はAnalyzeレベルの習得を目指し、対象は入社5〜10年目の中堅社員です。学習目的は、業務課題を構造的に捉え、改善の方向性を見出す力を育成することです。研修内では、分析フレームを用いて課題の構造を説明し、チェックリストの80%以上を達成することを学習達成度の基準とします。最終的には、実務で改善提案ができるようになることを目標とし、成果測定には提案件数、上司評価、業務改善指標を用いてください。研修手法は未定のため、ケーススタディ以外の選択肢も含めて提案してください。」 |
🛠️ 成果指標が曖昧な場合のプロンプト作成のポイント:成果指標もAIに提案させる
研修担当者がAIに研修設計を依頼する際、実務での成果指標(KPI)を明確に持っていないケースは多くあります。
その場合でも、BRIDGEモデルを使って研修の構造を整理し、成果測定方法の提案までAIに依頼することが可能です。
そのような場合のプロンプト作成のポイントは:
- 「成果測定方法も提案してください」という一文を加える
- 実務での成果が何かは曖昧でも、「業務改善につながる行動」などの方向性を示す
- 研修内での達成度(Degree)と、実務での成果(Evidence)を分けて記述する
✏️ プロンプト例(成果指標未定の場合)
| Bloom Level | Analyzeレベル |
|---|---|
| Role | 入社5〜10年目の中堅社員 |
| Intent | 業務における課題を構造的に捉え、改善の方向性を見出す力を育成する |
| Degree | 研修内の演習で、課題分析フレームを用いて論理的に課題の構造を説明し、チェックリストの80%以上を達成する |
| Goal | 実務で業務課題を構造的に分析し、改善の方向性を上司やチームに提案できるようになる |
| Evidence | 成果測定方法は未定のため、業務改善に結びつく行動や提案の質・頻度などを基に、適切な指標を提案してください |
| プロンプト文 | 「あなたは人材育成コンサルタントです。BRIDGEモデルに基づいて、中堅社員向けの業務課題分析力育成研修を設計してください。研修はAnalyzeレベルの習得を目指し、対象は入社5〜10年目の中堅社員です。学習目的は、業務課題を構造的に捉え、改善の方向性を見出す力を育成することです。研修内では、分析フレームを用いて課題の構造を説明し、チェックリストの80%以上を達成することを学習達成度の基準とします。最終的には、実務で改善提案ができるようになることを目標とします。成果測定方法は未定のため、業務改善に結びつく行動や提案の質・頻度などを基に、適切な指標を提案してください。研修手法も未定のため、ケーススタディ以外の選択肢も含めて最適な構成を提案してください。」 |
✅ このプロンプトのメリット
- 担当者がKPIを知らなくても、AIが業務文脈に応じた成果指標を提案できる
- 研修設計と成果測定が一体化され、実務への接続が強化される
- 手法の選定もAIに委ねることで、設計の幅が広がる
🧩 BRIDGEモデル活用テンプレート(AIへの研修設計依頼用)
ADDIEモデルでみてきたように、実務に役立ち、その成果を明確に定義した研修や学習の設計をするためには、ニーズ分析の際に組織ニーズやパフォーマンスニーズを明らかにすることが必須条件でした。組織や業務におけるKPIは、そのときに明確にすることができる場合もありますが、学習の成果指標とすべきことが曖昧なまま研修や学習の設計に入ってしまうこともあるかもしれません。
そこで、このプロンプトモデルを使って、成果指標が未定の場合でもAIに対して適切な学習設計依頼を可能にするテンプレートを用意しました。
設計者であるあなたは、BRIDGEモデルを適応して、以下のようにプロンプトを作成します。
“あなたは人材育成コンサルタントです。 [ 対象者 ] 向けの [ 研修テーマ ] 研修を設計してください。研修はBloomの [ 認知レベル ] の習得を目指し、対象は [ 対象者の属性 ] です。学習目的は、 [ 学習目的 ] です。研修内では、 [ Degree:達成度の基準 ] を満たすことを学習達成度の基準とします。最終的には、 [ Goal:業務でできるようになること ] を目標とします。[ Evidence:成果測定方法 ] については未定のため、業務改善に結びつく行動や提案の質・頻度などを基に、適切な指標を提案してください。研修手法も未定のため、最適な構成を提案してください。”
AI × BRIDGEで研修設計はもっとスマートに
BRIDGEモデルを活用することで、AIとの対話がより構造的・実践的になり、AIは単なるツールではなく、設計パートナーとして機能し、学習(研修)設計の質が向上します。成果指標が未定でも、AIに提案を依頼することで、現場に即した設計が可能になります。
研修設計担当者にとって、BRIDGEモデルは「設計力」と「対話力」を高める強力なツールです。今後の研修や学習コンテンツ設計に、ぜひ取り入れてみてください。
次回は、実際にBRIGDEを適応したプロンプトで作成されたコース例なども紹介しながら、AIによって作成されたコンテンツをブラッシュアップするポイントや考慮点を考察してみたいと思います。