第8回:学習目標の設定と評価戦略
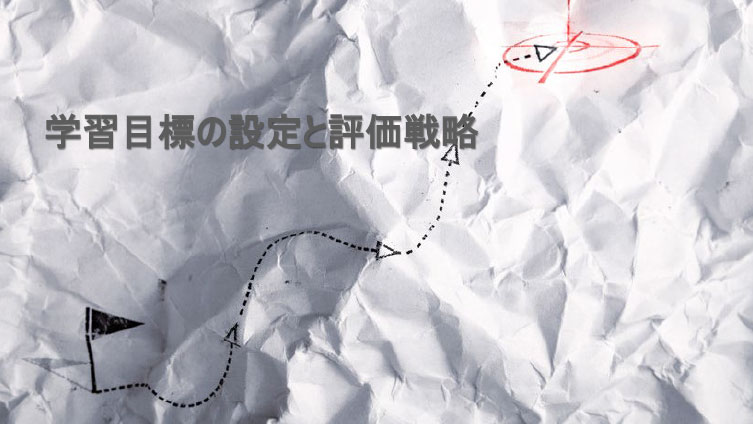
第7回では、適切な評価方法の選択や測定可能な学習結果を得るために必要な学習目標(習得目標)設定のABCDについて、説明しました。
今回は、ABCDモデルやBloomのタクソノミーを踏まえ、「学習成果をどう測るか」に焦点を当ててみます。
学習の成果を正しく測るには、学習目標の設計と評価戦略の構築が不可欠です。学習目標をどう設計し、それをどう評価につなげるかについて考えてみましょう。
🔍 学習目標と評価はセットで考える
まず確認したいのは、「学習目標」と「評価」は切り離せない関係にあるということです。
目標が曖昧であれば、評価も曖昧になります。たとえば:
- 「受講者は、コミュニケーションスキルを理解する」
→ 何をもって“理解した”と判断するのでしょうか? - 「受講者は、ロールプレイを通じて、上司への報告を3分以内に行える」
→ 行動が明確で、時間という達成基準もあるため、評価が可能です。
このように、測定可能な行動で記述された学習目標が、評価の出発点になります。
前回も良い学習目標の例と悪い目標の例を、クイズを交えて紹介しましたが、効果的な学習設計をするにあたってとても重要な要素なので、もう一度振り返ってみましょう。
⚠️ 悪い学習目標の例
- 受講者はリーダーシップの重要性を理解する。
- 社内メールの書き方を学ぶ。
- チームワークの大切さを知る。
- プレゼンテーションスキルを身につける。
これらの目標の問題点はなんでしょうか?
🔍 問題点:
- 「理解する」「知る」「学ぶ」などの曖昧な動詞が使われており、観察・測定が困難。
- 条件や達成基準が不明確で、評価設計に活かせない。
✅ 良い学習目標の例
- 受講者は、ケーススタディを用いて、部下との1on1面談の進め方を5分以内にロールプレイできる。
- 新入社員は、社内メールテンプレートを使って、上司への報告メールを敬語を適切に使って作成できる(正確率80%以上)。
- 部門長は、組織方針と自部門戦略の整合性を、15分以内にプレゼン資料を使って説明できる。
- 受講者は、模擬会議の場面で、アサーティブなフィードバックを3回以上実践できる。
🔍 良い点:
- 具体的な行動(Behavior)が明示されている
- 条件(Condition)と達成基準(Degree)があるため、評価可能
「理解する」「知る」などの抽象動詞を、「説明する」「実演する」「作成する」などに置き換えることがポイントでしたね。
🧠 組み合わせ設計の基本構造
ABCDモデルとBloomのタクソノミーを組み合わせた学習目標設計の具体例を考えてみましょう。
研修設計者にとって、行動の明確性(ABCD)と認知レベルの深度(Bloom)を両立させることは、評価設計やコンテンツ開発において非常に重要なことです。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| ABCDモデル | A: 対象者(Audience) B: 行動(Behavior) C: 条件(Condition) D: 達成基準(Degree) |
| Bloomのタクソノミー | 認知レベル:記憶 → 理解 → 応用 → 分析 → 評価 → 創造 |
📘 設計例:マネージャー研修の例
① 認知レベル:Understand(理解)
ABCD + Bloom目標(日本語)
受講者は(A)、SMART目標の5つの要素を(B)、講義資料を参照しながら(C)、80%以上の正答率で説明できる(D)。② 認知レベル:Apply(応用)
ABCD + Bloom目標
受講者は(A)、部下の職務内容に基づいてSMART目標を設定し(B)、ケーススタディを使って(C)、5分以内にプレゼンできる(D)。③ 認知レベル:Analyze(分析)
ABCD + Bloom目標
受講者は(A)、部下の過去の評価記録を分析し(B)、フィードバックの傾向を抽出するために(C)、3つ以上の行動パターンを特定できる(D)。④ 認知レベル:Evaluate(評価)
ABCD + Bloom目標(日本語)
受講者は(A)、部下の成果報告を評価し(B)、評価基準表を用いて(C)、納得感のあるフィードバックを記述できる(D)。⑤ 認知レベル:Create(創造)
ABCD + Bloom目標
受講者は(A)、部門の戦略目標に基づいて(C)、部下の行動変容を促すコーチング質問を3つ以上作成できる(B)(D)。
Bloomの動詞(e.g., explain, apply, analyze)をABCDのBehaviorに組み込むことで、深度と測定性を両立することができます。
以下は、Bloomのレベル別にABCDモデルを統合した目標を分類した表の例です。これによって、評価戦略も見据えた学習構造を作ることが可能になります。
| Bloomレベル | 学習目標 |
|---|---|
| Remember(記憶) | 受講者は、パフォーマンスマネジメントの主要用語を講義資料を使って80%以上の正答率で記憶できる。 |
| Understand(理解) | 受講者は、SMART目標の5要素を事例を用いて説明できる。 |
| Apply(応用) | 管理職は、部下の職務内容に基づいてSMART目標を設定し、5分以内にプレゼンできる。 |
| Analyze(分析) | 受講者は、部下の評価記録を分析し、行動傾向を3つ以上抽出できる。 |
| Evaluate(評価) | 管理職は、部下の成果報告を評価し、納得感のあるフィードバックを記述できる。 |
| Create(創造) | 受講者は、部門戦略に基づいて行動変容を促すコーチング質問を3つ以上作成できる。 |
上記のような学習目標を設定すると、学習結果として評価すべき内容が明確になりますよね。
学習者にとっては、学習で目指すべきこと、できるようになることと評価基準が明確に伝わるので、自分自身の学習過程で、自身の学習進捗状態を検証するための指標にもなります。
📐 ABCDモデルと評価の連動
ABCDモデルで設定した目標は、以下のように評価設計に直結します:
- Behavior(行動) → 観察・実演・ロールプレイで測定
- Condition(条件) → 評価場面の設計(例:ケーススタディ、模擬面談)
- Degree(達成基準) → 合格ラインの明示(例:80%以上、5分以内)
🧠 クイズ:この学習目標、整っている?整っていない?
✍️ Q1
- Bloomの行動動詞:✅ or ❌
- ABCDモデルの4要素:✅ or ❌
- あなたの評価は?
- A. 整っている
- B. 整っていない
✍️ Q2
- Bloomの行動動詞:✅ or ❌
- ABCDモデルの4要素:✅ or ❌
- あなたの評価は?
- A. 整っている
- B. 整っていない
✍️ Q3
- Bloomの行動動詞:✅ or ❌
- ABCDモデルの4要素:✅ or ❌
- あなたの評価は?
- A. 整っている
- B. 整っていない
✅ 解説
- Q1:整っていない → 「理解する」は抽象的で、行動として測定できない。ABCDのCとDも欠けている。
-
Q2:整っている
→ 「送信する」は具体的な行動動詞。
Audience, Behavior, Condition, Degreeすべてが含まれている。 - Q3:整っていない → 「学ぶ」「築くことの大切さ」は抽象的。行動としての記述が必要。
いかがでしょうか?
学習目標の設定が効果的な学習設計と学習成果を評価するために大切な基盤になるということを理解していただけたでしょうか?
もし、あなたが、今、何か研修や学習コースを企画している、コースコンテンツを作っているのであれば、自分の設計した学習目標をABCDとBloomの観点から当コラムに掲載されている表などを参考にしながら、校正してみてください。
次回は、カークパトリックの4段階評価モデル学習成果の定義についてご紹介します。